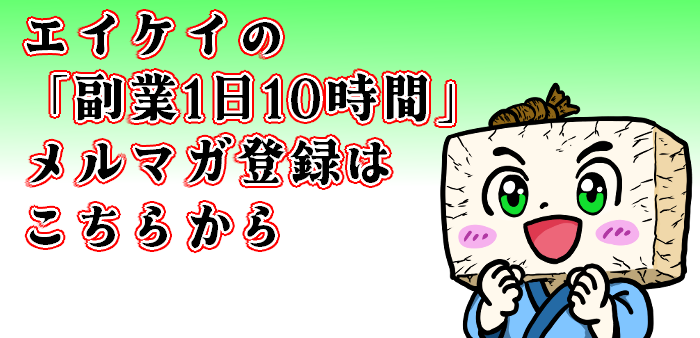1 期間工で即日退職はできる?初日バックレのリアルと注意点
「期間工って、入ったら辞めにくいんでしょ?」
「即日で辞めたらやばいよな…?」
そんな不安を抱える人は多いですが、実は“即日退職”は珍しいことではありません。
とくに入社1週間以内に辞める人はかなり多く、初日のバックレ率だけでも約30%に達するという声もあります。
たとえば、初日の安全教育だけ受けて「自分には無理そう…」と判断してそのまま去ってしまう人も。
期間工は想像と現実のギャップが大きく、慣れる前に折れてしまう人が多いのも事実です。

とはいえ、バックレではなく「辞めたい」と伝えることで、法的にも即日退職は可能です。
大事なのは、黙って消えるのではなく、きちんと伝えること──それだけでトラブルの9割は回避できます。
1-1|なぜ即辞めしたくなる?初日〜初週で起こる“ギャップの壁”
期間工で「辞めたい」と感じるタイミングは、圧倒的に“初日〜初週”が最多。
これは、実際に現場に入ってみて、事前に聞いていた内容や自分のイメージとの間に
強烈なギャップがあることが原因です。
よくある“初期で辞めたくなる理由”はこんな感じ
-
安全教育の内容が想像以上にハードで絶望
-
寮生活がストレスだらけ(共同生活・古さ・騒音)
-
工場の空気・音・雰囲気が合わない
-
立ちっぱなし作業や持ち上げ作業が想像よりキツい
特に、「ライン作業なんてすぐ慣れるだろ」と思っていた人が、
初日で“無理ゲー”を感じて心が折れるのは、ほんとによくあるパターン。
最初の1週間をどう乗り越えるかが、継続するかどうかの大きな分岐点です。
1-2|期間工のバックレ率は?データで見る即日退職の現実
某メーカー人事の体感では、入社1週間以内の離職率はおよそ30%。
さらに詳しく見ると、以下のような感じ
| 退職タイミング | 離職率 |
|---|---|
| 初日〜1週間 | 約30% |
| 2週間以内 | 約20% |
| 1ヶ月以内 | 約10% |
| 3ヶ月以内 | 約5% |
この数字からもわかるように、期間工は「続けられるかどうかは最初の1週間で決まる」と言っても過言ではありません。
逆に言えば──
1ヶ月耐えられれば、あとは慣れるパターンが多いってことでもあります。
2 「辞めたいけど言い出せない…」そんなときは誰にどう相談すべき?
「辞めたいけど、どう切り出したらいいのか分からない…」
「係長が怖くて話しかけられない…」
そんな悩み、めっちゃわかります。
実際、期間工の現場では“言い出せずに我慢する”→“精神的に限界”→“バックレる”って流れ、多いんです。
でもちょっと待って。
辞めたいときほど、誰にどう相談するかでその後が大きく変わるんです。
仕事はバックレが一番よろしくないですし、期間工などに関してはやめたいと言ったらすぐに辞められることのほうが多いです。
2-1|係長が怖いなら、まずは“班長 or 職長”に相談しよう
係長って、現場にはあまり顔を出さないし、ちょっと距離感ある存在ですよね。
「いきなり係長に言うのはハードル高すぎる…」って人は多いです。
そんなときこそ、班長や職長に相談するのが◎
現場で一緒に作業している分、話しかけやすいし、あなたの状況もある程度理解してくれてることが多いです。
ポイントは「相談」→「報告」へ
-
「実は最近、体調がしんどくて…」
-
「ちょっと精神的に限界かもで…」
こんなふうに、“辞めたい”をダイレクトに言う前に、相談ベースで話すのがコツ!
部署によっては自分に合わないということは往々にしてありまして、その場合は相談するとすぐに異動できることもあります。
自分の見た中では23歳くらいのガチムチな男の子が「この部署は身体を動かさな過ぎて嫌だからもっとキツイところがいい!」と異動をしてました。
それはそれで凄いですよね笑
2-2|揉めずにスパッと辞める!円満退職に使える“理由テンプレ”
-
「辞めます!」と感情的に伝えると、余計な摩擦が起きがち。
だからこそ、“スッと伝えて、スッと辞める”ための理由付けが超大事。以下のような建前でOKなフレーズがめちゃくちゃ使えます
使える退職理由テンプレ集:
-
「家族の体調が悪くて急遽帰省することになった」
-
「持病が悪化して長時間の勤務が難しくなった」
-
「医師からストレス性の症状が出てると言われ、しばらく静養が必要になった」
こうしたフレーズを使えば、相手も無理に引き止められません。
ぶっちゃけ、“本音”より“建前”の方がスムーズに辞められるのが現実なんです。実際、現場の人たちも「即日辞め」はもう慣れっこ。
期間工や派遣って、会社も「代わりはいくらでもいる」って考えが基本なんで、
気負わず、ちゃんと順序だけ守って辞めればOK! -
3 バックレは絶対NG!知らずに損する3つのリアルなデメリット
「もうバックレちゃおうかな…」
そう思ったことある人、多いと思います。
でも実際、バックレ退職には“想像以上のデメリット”があるんです…。
ここでは、「知らなかった…じゃ済まない」リスクを3つ、わかりやすく紹介していきます
3-1|社会保険が止まらず“10割負担”に!?
バックレると、会社側での社会保険の脱退処理がスムーズにされません。
そのままだと「会社に在籍してる扱い」のままになり、健康保険証も無効状態に。
そうなるとどうなるか・・・
なんと、病院に行ったときの医療費が、全額自己負担(10割)になるリスクがあります!
例:風邪で病院
→ 本来3,000円の診察が → 10,000円オーバー
軽症でも普通に1万超えるレベルなので、
「辞めたあとこそ保険の整理は大事」というのが現実です。
3-2|懲戒解雇扱いで“履歴書に傷”が残る恐れも
もし会社がバックレ行為を「悪質」と判断した場合、
懲戒解雇という最も重い処分になる可能性があります。
これは単なる「自己都合退職」とは違って、
👉 履歴書に正直に書いたらめっちゃ印象悪くなるやつです。
転職の際に「なぜ辞めたんですか?」と聞かれて、
「バックレました」と答えるわけにもいかず、ずっとモヤモヤを抱えることにも…。
懲戒解雇になると
-
再就職で不利になる
-
派遣会社の“社内ブラックリスト”入りする
-
下手すると系列グループにも情報共有される
「バレなきゃOK」と思っている方!?
安心してください!甘すぎる考えですよ!!
バレますよ!!
3-3|失業保険が3ヶ月遅れに
期間工をしっかり満了して辞めれば、
基本的に「会社都合退職」扱いで、待機7日で即支給開始になります。
でも、バックレや自己都合で辞めた場合は…
3ヶ月間、失業保険がもらえない給付制限がかかるんです!
この3ヶ月間って、収入ゼロのまま耐えなきゃいけない時期。
しかも、ハローワークで「バックレました」なんて正直に言えないので、説明もややこしくなります。
ちなみに実体験では・・・

バックレは短期的にはラクに思えても、
中長期で見ると【金・信用・未来】を全部失う行為です。
ダメ!ゼッタイ!!!
4 スムーズに辞めたい人へ!期間工の正しい退職ステップ
バックレはリスクが大きすぎる──
それがわかったら、あとは「正しい辞め方」を知っておくだけ!
実は期間工の退職手続きって、
想像よりずっとシンプルでスピーディーなんです。
4-1|即日退職も可能!最短で辞めるための流れと準備
辞めると決めたら、まずやることはひとつ。
係長・班長に「辞めたい」と伝えるだけ。
それだけで、もう辞める準備に入ります。
あとは以下のような流れで進んでいきます
最短退職の流れ
- 現場の上司(係長・班長)に退職の意思を伝える
- 人事部との面談・退職届の提出
- 寮の荷物整理・会社備品の返却(作業着・社員証など)
-
最短で“翌日退寮” → 2日で退職完了するケースも!
期間工は「人が足りないからこそ募集してる」仕事なので、
やる気のない人を無理に引き止めようとは思っていません。
つまり、辞めたい人をサクッと辞めさせるのが会社的にも都合がいいってことなんです!
4-2|辞めたあとに住む場所がない…そんな人が即やるべき行動
「辞めたら寮を出なきゃいけない…」「でも行く場所がない…」
──この悩み、意外と多いです。
でも大丈夫。
そんな人にこそおすすめなのが、即入寮可能な仕事紹介サービスの活用です!
派遣も期間工も基本的には紹介会社に登録してから行くのが多いと思います。
そして大体が寮などのすぐに住み込みで働くことができる状態になっているのがほとんど。
登録しておけばすぐ「次の仕事+寮」を紹介してくれます。
しかも、過去の勤務態度(遅刻ナシ・無断欠勤なし)などを見て、入寮時に優遇されるケースもあるんです!
ちなみに実体験では・・・

辞めたあとこそ、「住む場所と収入の確保」が最優先。
ちゃんと動けば、1日で次の生活に切り替えられます!
5 即日退職でも再就職できる?転職への影響とリカバリー術
「即日で辞めたら次の仕事どうなんの?」
「また期間工できるの?ブラックリスト入りじゃね?」
──これ、めっちゃ気になるよな。
結論から言うと、**辞め方次第で“全然OK”**です。
ただし、ポイントを押さえないと転職で不利になることもあるので、しっかりチェックしよう!
5-1|出戻りは難しい?同じメーカーへの再雇用は要注意
まず大前提として、即日退職したメーカーへの“出戻り”はめちゃくちゃハードル高いです。
特に、「祝い金だけもらって即退職」みたいなやり方は完全にアウト。
もちろん再雇用が絶望的になるのはバックレた場合の話です!満了したら寧ろ出戻りは歓迎されます!
なぜ出戻りNGなのか?
-
勤怠や退職理由は企業側に記録が残る
-
悪質と判断されると、系列グループ全体での採用NGの可能性も
-
派遣元からも「要注意人物」として扱われることも…
- 祝い金(入職1か月くらいで10~20万くらいもらえたりする)だけをもらって
すぐに次の祝い金を狙うのは悪質行為とみなされるため。
つまり、即日退職した会社には戻らない前提で動くのがベター!
5-2|履歴書に書く?書かなくてOK?バレる可能性は?
「即日退職した経験、履歴書に書いた方がいいの?」
これ、気になる人めちゃくちゃ多いけど、実は…
書かなくても問題ないケースが多いです!
履歴書に書かなくていいケース
-
勤務期間が1週間未満 or 社会保険に未加入
-
給与の支払いや雇用保険記録が残っていない
-
バレても問題にならない規模の勤務(バイト扱い)
逆に、保険加入や給料の支払いがあって記録に残ってる場合は、
“空白期間”にならないように、あえて軽く書いておくのもアリやで!
5-3|派遣会社との関係を壊さないために守るべき3つのコツ
期間工は派遣会社との信頼関係が命。
時には本当に職場がヤバすぎてすぐにでも辞めたいときもあるでしょう。
なので、もし次の仕事も紹介してもらいたいなら、辞め方で信頼を失わないことが超大事!
派遣会社に嫌われないコツ
-
「辞めたい」と必ず事前に連絡する(無断退職は絶対NG)
-
理由は“体調・家族・メンタル”などでOK(嘘でも建前で◎)
-
「また働きたい気持ちはある」と前向きさを見せる
派遣会社も辞められることには慣れてるけど、
「辞め方」が雑だと、次に紹介される確率がガタ落ちします!
6 期間工を辞めた人が実際に選んでいる3つのキャリアパス
「期間工辞めたあと、どうすればいいの?」
「次に何やるか決まってなくて不安…」
そんな人のために、実際に多くの元期間工たちが選んでいる進路パターンを3つ紹介するで!
6-1|体力に不安…そんな人は楽な職場へ
期間工を経験した人の中には、「もうあんな体力仕事ムリ!」という人も多いはず。
そんな人に選ばれているのが
-
倉庫内の軽作業
-
シール貼りや検品などの短時間作業
-
受付・事務などのデスクワーク
自分も年齢も年齢ですからずっと期間工で働けるわけはないですしね・・・。
どこかで体力に見合った仕事にしなくてはいけないかもしれません。
ちなみに実体験・・・最初は楽だったんですが・・・

人によって感じ方はさまざまやけど、
「次は自分のペースで働きたい」っていうニーズはめっちゃ多いと思います!
6-2|スキルを活かす or 手に職をつける業界へ
「期間工じゃ将来が不安…」「何か武器がほしい」って人には、
スキルが身につく職種への転職や、資格取得が人気。
実際に多い進路例
-
建設・整備・溶接などの技術職
-
フォークリフト免許を活かした物流職
-
製造系からCADなどへの転向
ただし、ぶっちゃけ期間工で得られるスキルは少なめ…というかほぼないと言っても過言ではありません。
ただ、自分のように介護から工場勤めをしてみて「こういう仕事もやれるんじゃん!」と感じて新しい道に行くことも可能だと思います。
「次の職場で育ててもらう前提」で動くのが吉!
6-3|期間工で貯めたお金で“副業・起業”へチャレンジ!
期間工のメリットのひとつが「短期間でしっかり稼げる」こと。
うまくやれば、1年で50〜100万円の貯金ができる人もザラ。
それを元手に、こんな道を選ぶ人も
-
副業ブログや動画編集をスタート
-
個人で軽配送ドライバーに転身
-
小さなネットショップを開業
-
貯金で数ヶ月分の生活費を確保 → 本気でやりたいことに挑戦
ちなみに実体験・・・

「ただ辞める」だけじゃなく、
次のステップを選べる状態で辞めるのが大事なんです!
7 まとめ:バックレず辞めれば“その後の人生”が変わる!
期間工って、ぶっちゃけしんどいです。
人によっては仕事内容も合わなきゃ、寮での半分集団生活も辛いという人もいるでしょう。
体力的にも精神的にも追い詰められて、
「もう無理!バックレたい!」って気持ちになるのも、めっちゃわかる。
でも──
辞める=悪じゃない。
バックレる=“損しかない”ってだけ。
実際に、即日退職でもちゃんと伝えさえすれば、
✅ 社会保険もスムーズに脱退できる
✅ 失業保険もすぐもらえる
✅ 派遣会社からの紹介も受けられる
✅ 信頼関係も保てる
っていうメリットだらけの辞め方ができるんです。
期間工を辞めたあとが、むしろチャンス
-
体に優しい仕事へ転職
-
スキルアップや資格取得
-
貯金を元手に副業・起業チャレンジ
期間工は「人生の一時避難所」にもなるし、
「次に向けての準備期間」にもできる。
そして最後に伝えたいのは、

ってこと。
バックレたら損しかない。
でも、正しく辞めれば、ちゃんと次のチャンスが拾える。
辞めることに後ろめたさを感じなくていいんです。期間工なんてそういうものなんですから!
でも、社会に生きるものとして正しい退職だけは忘れないでくださいね。
もしこの記事を読んで「よし!辞めよう!」ってなった方!
あなたの次の一歩を、応援してます!!!